こんにちは。地域包括ケアシステム.comの成冨です。
今回は「今からでも遅くない!2025年版チームオレンジ攻略方法」と題して、これまでの取り組みを振り返りつつ、最新の進め方を整理しました。
動画解説
これまでの流れと現状の課題
私はこれまで、2020年からチームオレンジの整備方法、オレンジチューター研修、コーディネーター研修の進め方、さらに2022年の「チームオレンジを軌道に乗せる方法」、2023年の「実践攻略解説」といった形で解説を続けてきました。
しかし、それでも「うちの地域は全然進みません」という声を多く耳にしました。
つまり、情報はあっても現場に落とし込めていない、成果につながっていない市町村が多いのです。
よくある課題
-
運営体制を作ったものの、会議だけで動きが停滞している
-
ステップアップ講座を開催したが、その後の活動の輪が広がらない
-
ボランティアや職域サポーターを探しても見つからない
-
認知症本人や家族を探そうとしても出会えない
-
結果として「どこから手をつけていいかわからない」まま数年が経過
そして、「成果を出せ」と求められる一方で、人もお金もいない現実に苦しんでいる…。
そんな現場の声が積み重なっているのです。
問題の本質:「知らない・つながっていない」
私は、この問題の本質は「資源がないこと」ではなく、「知らない・つながっていないこと」だと思っています。
実は、すでに多くの取り組みが存在しています。
-
困りごと支援は、生活支援コーディネーターが整備済み
-
個別支援は、地域包括支援センターが日常的に実施
-
認知症カフェやサロン、ボランティア活動も各地で継続
つまり「新しい仕組みをゼロから作る必要はない」のです。
あるのに知られていない。つながっていない。それが一番の課題なのだと思います。
解決の2つの視点
そこで解決のために重要なのは、たった2つの視点です。
1. 地域にすでにある力を活かす
チームオレンジを立ち上げる際に「ゼロから新しく作る」と考えると、どうしてもパンクしてしまいます。
大切なのは、既に存在している取り組みを再編し、役割分担を見直すことです。
例として:
-
見守り・声かけ・生活支援 → 生活支援コーディネーター
-
個別の相談・専門職につなぐ → 地域包括支援センター
-
サロン・カフェ運営 → 地域団体や住民ボランティア
このように整理していくと、「自分たちが何をすべきか」が明確になり、心が軽くなります。
2. 眠っている機能を目覚めさせる
さらに大切なのは、眠っている力を呼び覚ますこと。
-
グループホーム
本来「地域の認知症ケア拠点」として期待されているのに、入居施設の役割に留まっているところが多いのが現実です。
しかし、学習会や交流会を開く場としては最適です。 -
社会福祉法人
地域で公益的な取り組みを行うことが求められているものの、十分に発揮されていない場合もあります。
地域協議会での話し合いや連携の場を広げることが、眠っている力を引き出すきっかけになります。
「学び」「相互理解」「交流」――この3つを地域に開くことで、チームオレンジの活動は自然と広がっていくのです。
小さな一歩がドミノのように広がる
地域づくりは、一気にすべてを動かす必要はありません。
例えば、50のグループホームがあっても、まずはそのうちの1か所が動き出せば良いのです。
そのための根拠となる資料↓
さらに、意向確認チェック表まで今回は特別にお伝えします↓
たった1つの動きが、他の地域に「自分たちもやらなければ」という意識を生み、ドミノのように広がっていきます。
地域の変化は、まずは一歩から始まるのです。
実際にどう動くのか?
① 運営拠点の立ち上げと自立:グループホーム・社会福祉法人を拠点にチームオレンジを運営する。
② 認知症ケアの地域拠点化:本人・家族・地域をつなぎ、解決へ導く機能を発揮する(フォーマル・インフォーマル)。
③ 人材の活躍と多職種連携:ステップアップ講座修了者の活躍の場を設け、多職種連携の機会とする。
④ 情報発信と予防・早期支援:活動を広く伝え、普及啓発につなげ、予防・早期発見を支援する。
まとめ
-
課題は「知らない・つながっていない」こと
-
解決には「既存の力を活かす」「眠っている機能を目覚めさせる」ことが重要
-
すべてを一気に動かす必要はなく、1つの拠点から始めれば広がっていく
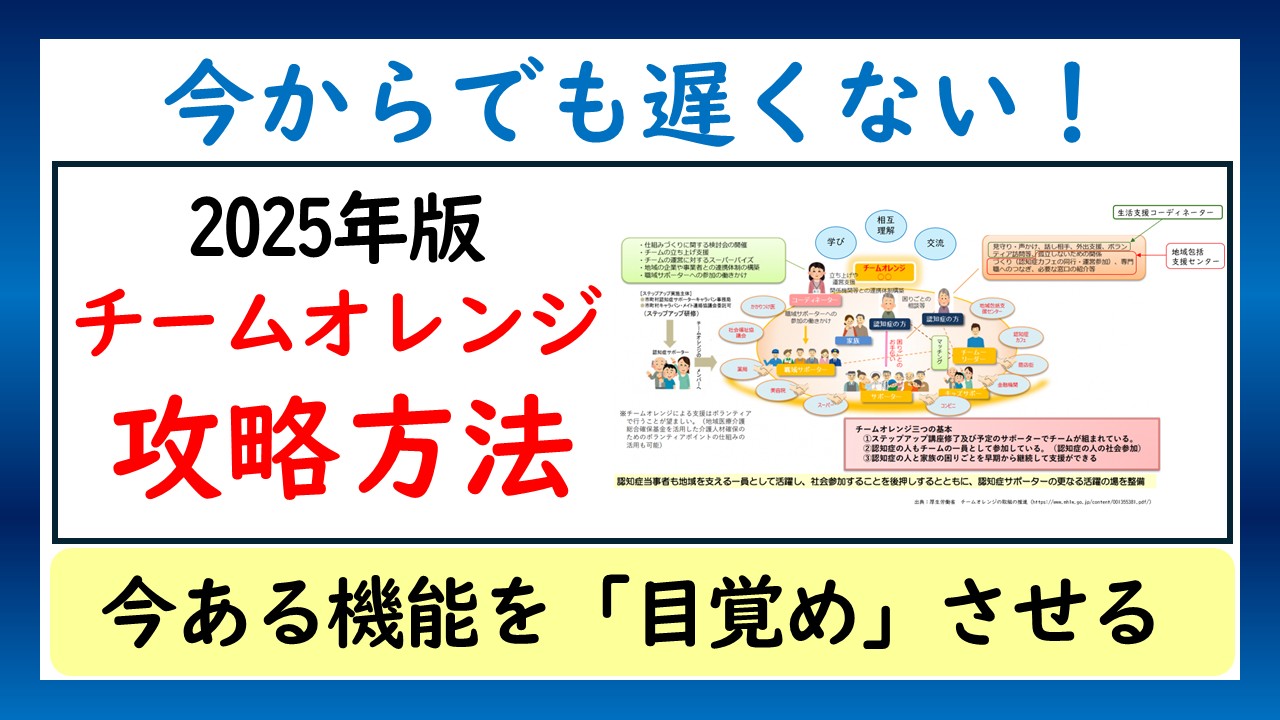
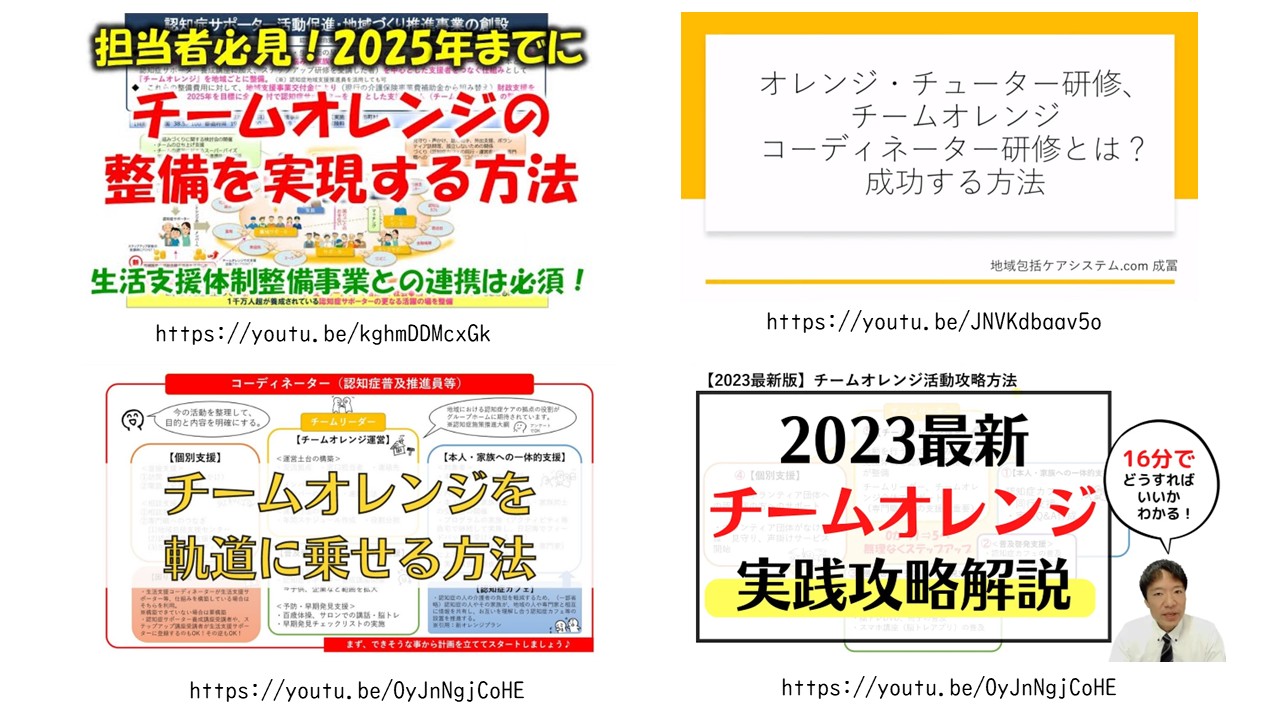
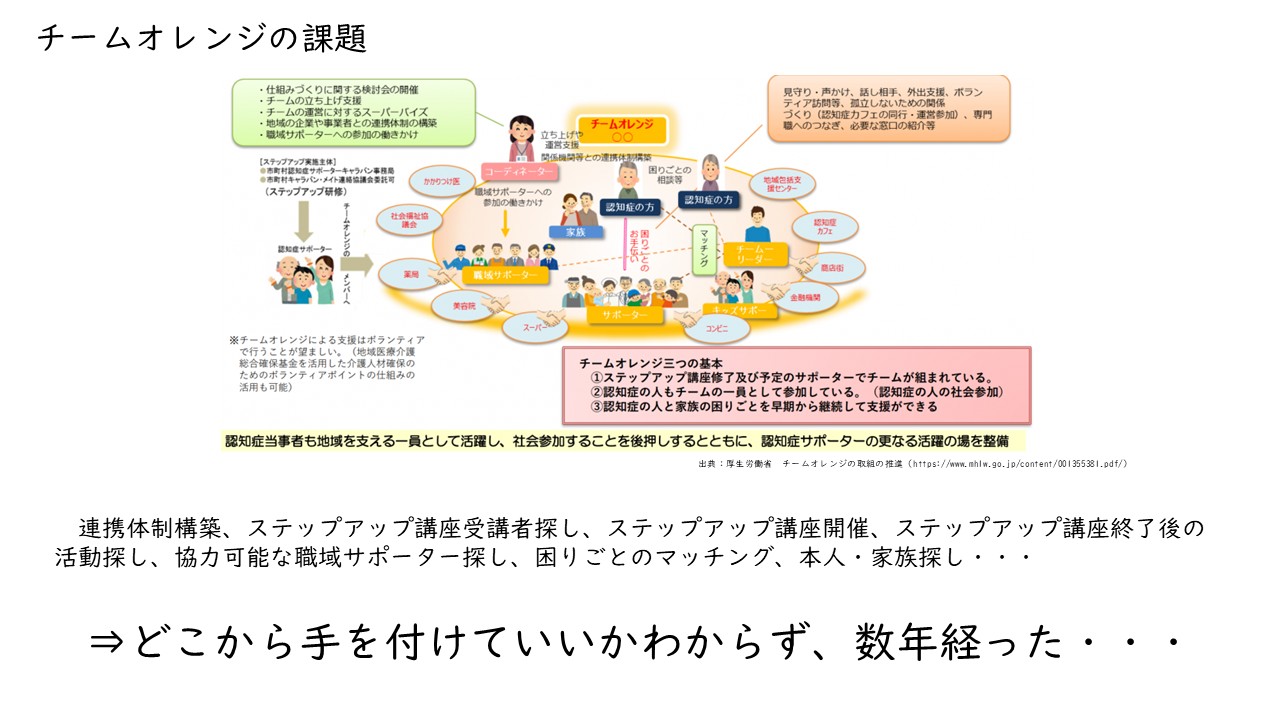
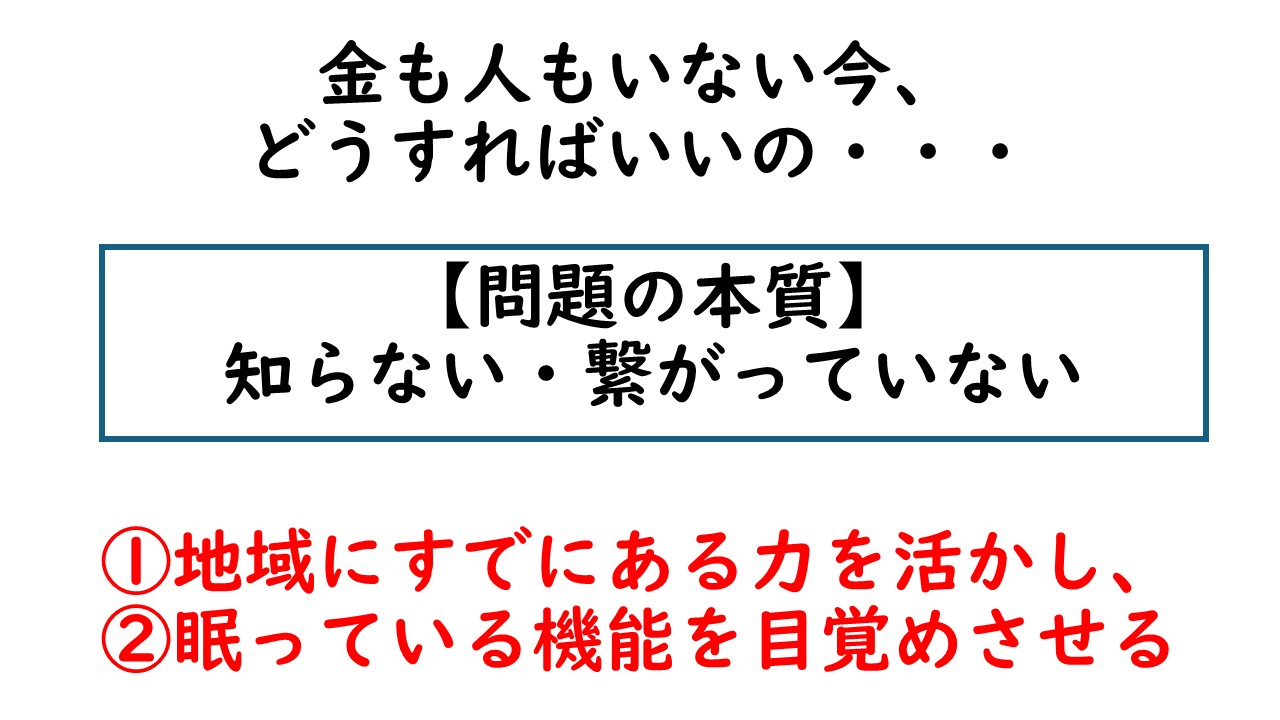
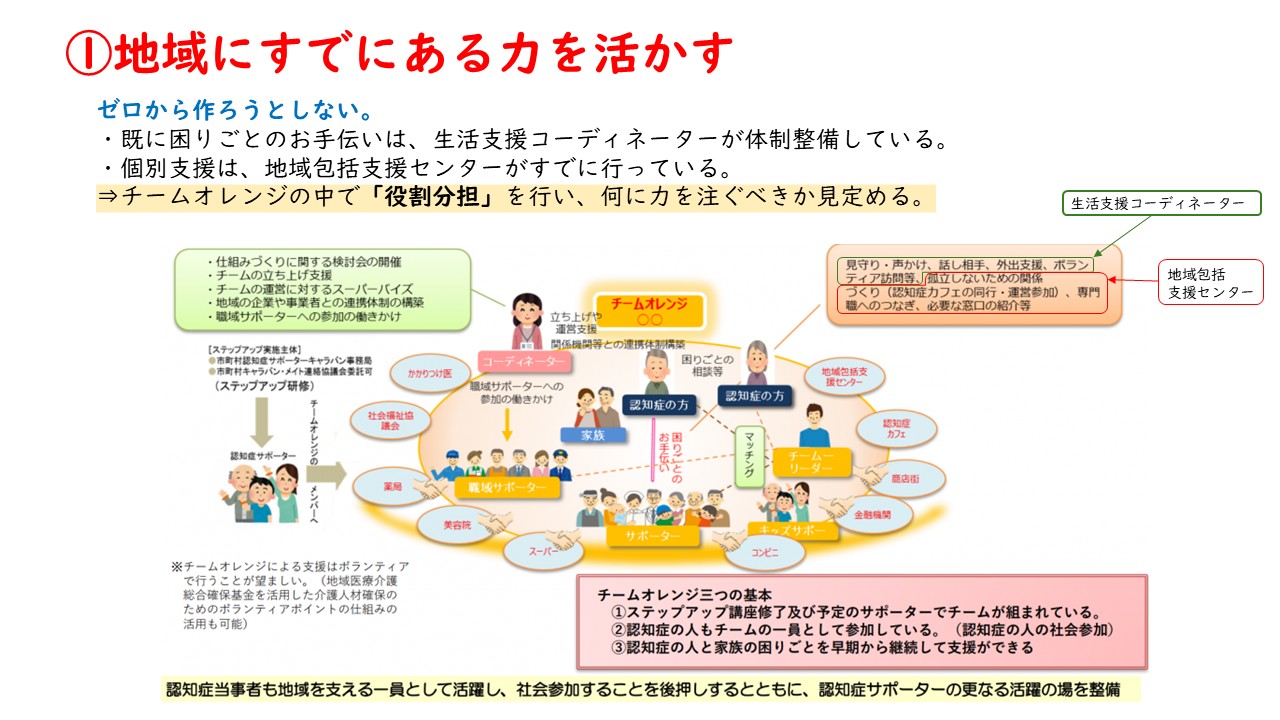
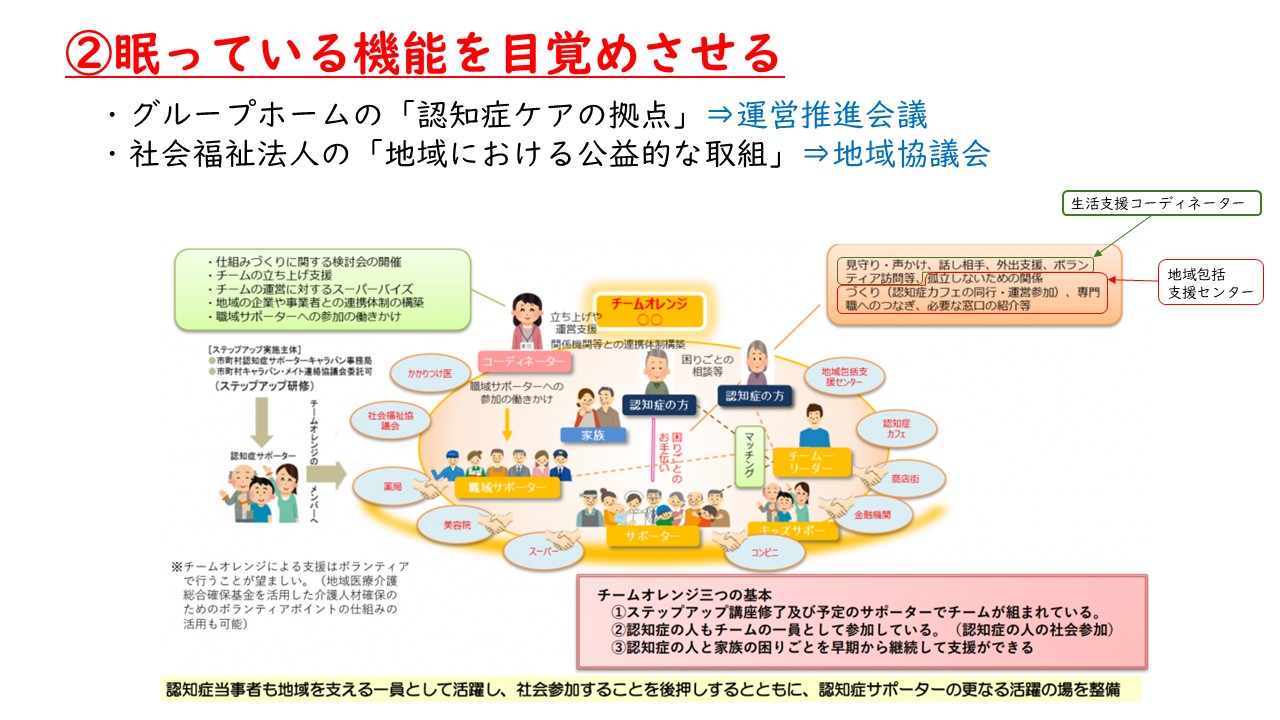
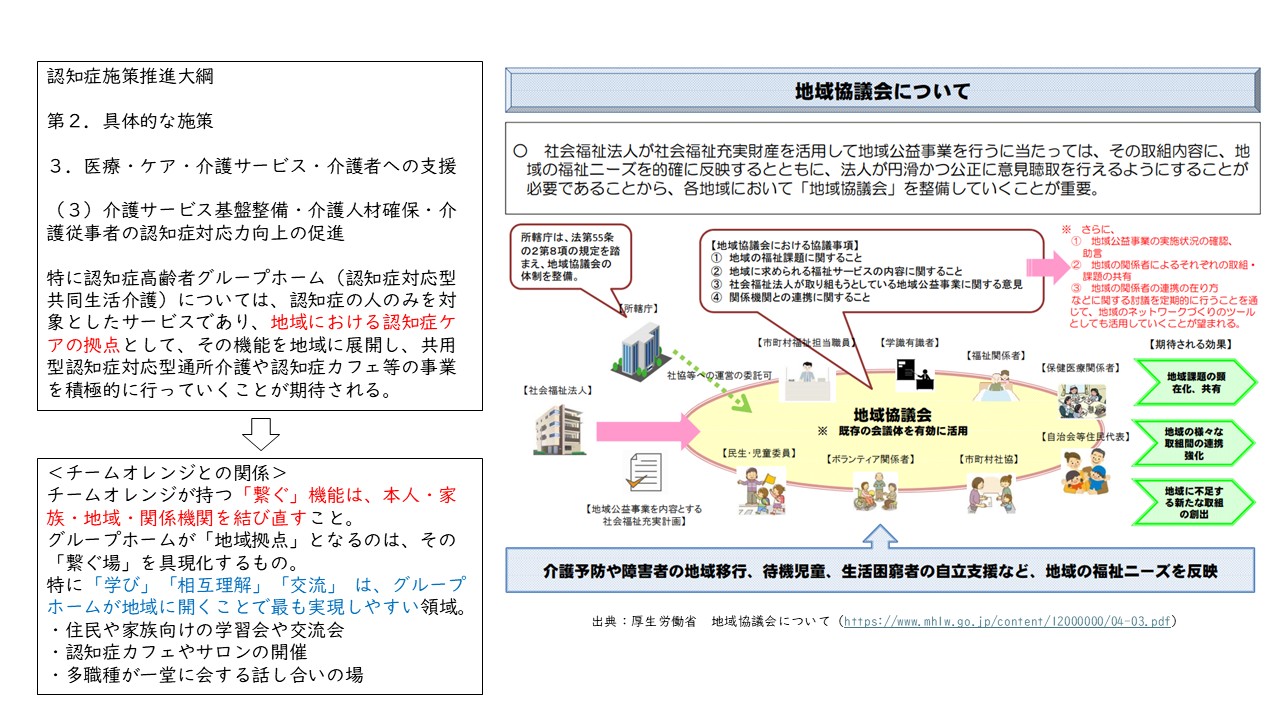
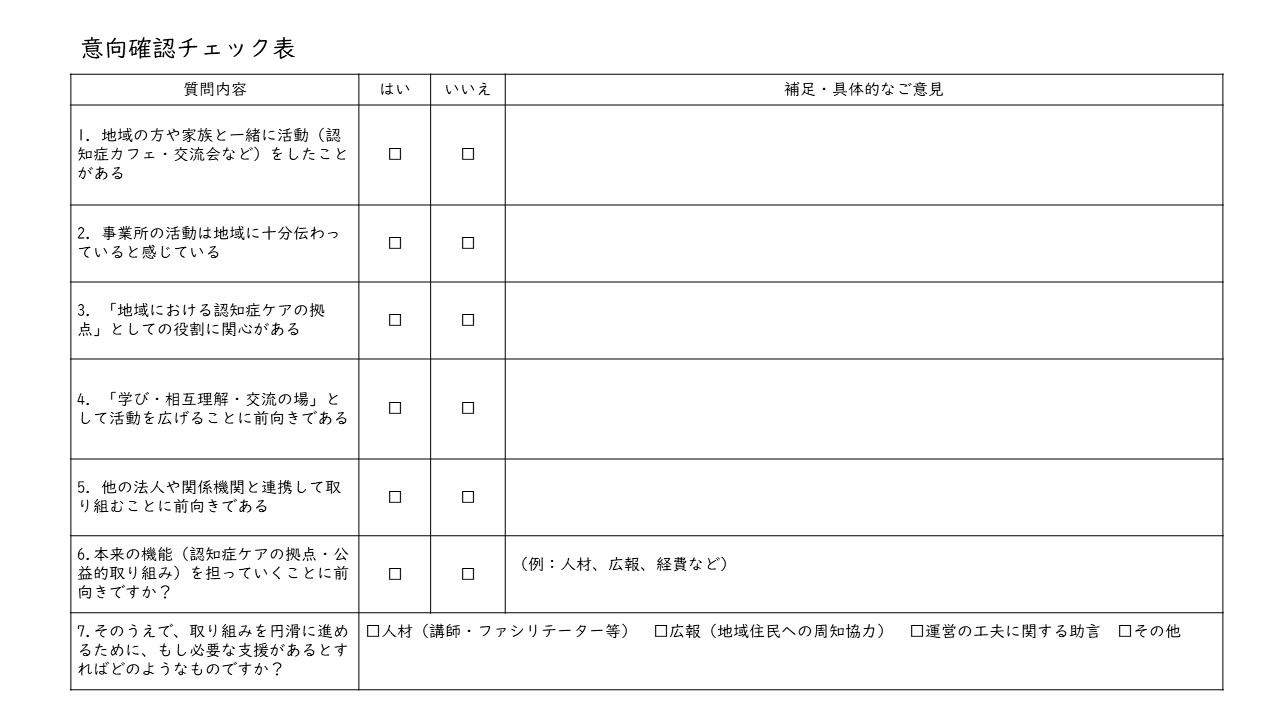
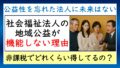
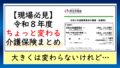
コメント